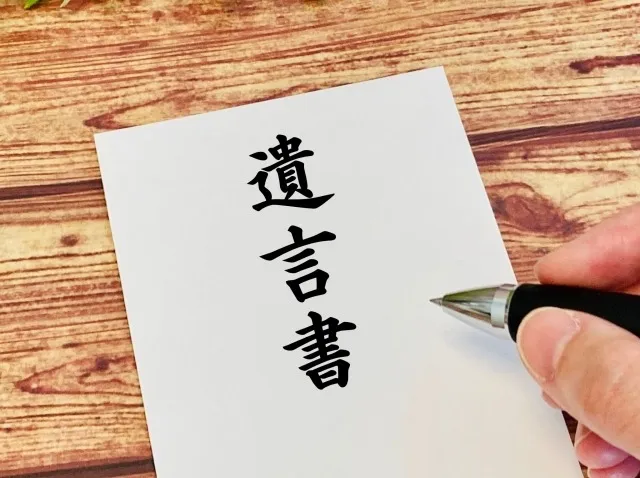【コラム】遺言書の基本と選び方~3つの形式と作成時の注意点を解説~
2025/04/03
相続に関するトラブルを防ぎ、大切な財産を確実に引き継ぐためには、「遺言書の作成」が効果的です。しかし、どの形式を選べばよいのか、作成時にどのような点に注意すべきか悩まれる方も多いのではないでしょうか。当記事では遺言書の3つの形式それぞれの特徴や選び方、さらに作成時の重要な注意点について解説していますのでご一読いただければと思います。
遺言書の種類と選び方
遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの種類があります。どれを選んでもかまいませんが、特徴が異なりますのでご自身の状況に合わせて選択すると良いでしょう。
特に選ばれることが多いのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は文字通り遺言者が全文を自筆で作成する方式で、手軽に作成できる反面、形式不備による無効のリスクが大きいという難点を持ちます。一方、公正証書遺言は公証人の関与のもと作成されるため法的な安定性が高いものの、一定の費用が必要となります。
どの遺言書を選ぶべきか、遺言者の状況によって異なります。例えば相続人間で争いが予想される場合や、財産が複雑な場合は、法的安定性の高い公正証書遺言が適しています。また、高齢の方や病気がある方も、専門家のサポートが受けられる公正証書遺言が望ましいでしょう。
他方、費用面では自筆証書遺言がもっとも経済的です。無料で作成でき、法務局での保管制度を利用する場合でも3,900円の負担で済みます。公正証書遺言は遺産額に応じて費用が変動し、数万円以上は必要となるでしょう。秘密証書遺言では手数料が一定で、11,000円かかります。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、3つの遺言方式の中でも手軽に作成できることから、多くの方に選ばれています。
特別な費用をかけることなく作成でき、公正証書遺言のように証人を立てる必要もないため、「遺言の内容を他人に知られることなく作成できる」点が特徴です。また、いつでも自由に書き直しができるため、財産状況や家族関係の変化に応じて柔軟に対応することができます。
その一方で、作成時には細心の注意が必要です。遺言書の本文はすべて遺言者本人が自筆しなければならず、パソコンでの作成や、家族による代筆は認められません。
※財産目録に関しては別紙でパソコン作成が可能。作成日付と氏名を自書のうえ押印をする必要がある。
このような特徴から、自筆証書遺言は遺言の内容を秘密にしたい方、費用を抑えて遺言書を作成したい方、比較的単純な内容の遺言を残したい方に適しているといえます。
自筆証書遺言保管制度について
2020年にスタートした自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言の大きな課題であった「紛失・改ざんのリスク」を解決する有益な制度です。法務局で原本と画像データを保管するため、紛失や盗難、偽造、改ざんの心配がありません。また、火災や自然災害からも遺言書を守ることができます。
さらに、法務局で遺言書の形式的要件がチェックするため、方式不備による無効のリスクも低減できます。そして相続開始後は、法務局から相続人に対して遺言書の保管の有無を通知することも可能なため、遺言書の存在を知らないまま相続が進んでしまうリスクも防ぐことができるのです。
自筆証書遺言のデメリットを大きく補完する制度ですので、自筆証書遺言を選択しようとしている方は、こちらの制度の利用も前向きに検討すると良いでしょう。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言では、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人がそれを筆記して作成していきます。作成の際には2名以上の証人の立会いが必要となりますが、法的な安定性がもっとも高い遺言方式として知られています。
大きな特徴として、「遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きが不要」な点を挙げられます。また、原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。
なお、公証人は遺言の内容そのものについてのアドバイスは行わないため、内容面での相談は司法書士などほかの専門家に依頼する必要があります。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在を公的に証明できる遺言方式です。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的性質を持ち、遺言の内容を秘密にしたい場合でも、一定の法的安定性を確保できる方式となっています。
この方式の大きな特徴は「遺言書の作成にパソコンを使用できる」点にあります。ただし、作成後は遺言書を封筒に入れて封印し、公証人1名と証人2名以上の面前で提出しないといけません。この手続きに手数料が発生しますし、自筆証書遺言のように1人では作成手順を完結させられません。
また、公正証書遺言とは異なり原本は遺言者自身で保管する必要があります。そのため、遺言書の紛失や破損を防ぐため、保管場所には特に注意を払う必要があります。銀行の貸金庫を利用したり、信頼できる第三者に預けたりするなどの対策を検討するとよいでしょう。
なお、この遺言方式は他の2つの方式に比べて利用頻度が低いのが現状です。これは、手続きの複雑さや保管上の課題、相続時の検認手続きの必要性などが理由として考えられます。
共通の注意点
遺言書を作成する際、その種類を問わず注意すべき重要なことがあります。押さえておきたいポイントを下表にまとめましたのでチェックしておいてください。
|
注意点 |
重要ポイント |
詳細 |
|
遺言能力の有無 |
・障害の有無 ・15歳以上かどうか |
精神障害等により判断能力を欠く状態での作成は無効となる。認知症の懸念がある場合は医師の診断書を準備するなどして遺言能力が示せる状態で作成すべき。 |
|
財産の特定 |
相続財産を明確に記載すること |
不動産であれば所在地・地番など詳細を記載して確実にどの物件を指しているのか分かるように記載する。預貯金でれば金融機関名・支店名・口座番号などを明記する。 |
|
遺留分への配慮 |
相続財産が偏り過ぎないようにする |
法定相続分と遺留分の計算を正確に行い、相続分の指定や遺贈によって特定の相続人が持つ遺留分を侵害しないようにすべき。遺留分の侵害があると受遺者等が金銭の支払いを求められることもある。 |
|
保管方法 |
安全な保管場所の確保と周知 |
公正証書遺言以外の場合、安全性の高さに配慮し、併せて相続開始後の未発見のリスクも回避できるような保管方法を検討すべき。 |
|
遺言執行者の必要性 |
信頼できる人物を選ぶ |
相続人らに所有権移転に係る手続きを任せたのでは不安があるという場合、遺言書に遺言執行者を定めておく。法律の専門家など専門知識を持つ人物が望ましい。 |
|
内容の見直し |
定期的に確認し、必要に応じて内容を更新する |
何年も前に作成した遺言書だと、すでに受遺者が亡くなっていたり推定相続人が変わっていたりすることもある。そこで定期的に見直して、必要なら内容を更新する。 |
遺言書をめぐるトラブルも少なくありません。上記の点に十分注意を払い、必要に応じて専門家に相談すること、ご家族としっかり話し合って作成おくことをお勧めします。
----------------------------------------------------------------------
相続専門のあかりテラス
住所 : 熊本県熊本市東区御領2-28-14 大森ビル御領203
営業時間:平日 9:00 ~ 18:00
土日祝もご予約でお受けいたします
電話番号 : 096-285-6841
----------------------------------------------------------------------